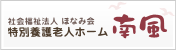ホーム > 理事長エッセイ > 10 記憶していなければ答えられないことを質問してはいけない
10 記憶していなければ答えられないことを質問してはいけない
ふだん面会に訪れるご家族の多くが、認知症の老親(入居者)にむかって同じような言葉をかけています。どのような言葉かというと、顔を合わせるなり、「わたしが誰だかわかる?」と尋ねるのです。そこで、以下のような会話を作ってみました。
例1: 施設で暮らしている認知症の母親と、毎日面会に訪れる娘の会話
娘「お母さん、面会に来ましたよ。わたしが誰だかわかる? 名前を言ってみて?」
母「 ... 」
娘「どうしたのよ。わたしの名前を言ってみて」
母「 ... 」
娘「忘れちゃったの? だめじゃない。自分の娘でしょう! わたしの名前は?」
母「 ... どうしてそんなことを聞くの? ... 」
娘「しっかりしてよ。忘れちゃダメでしょう! 思い出して言ってみて」
母「 ... いいじゃない、そんなこと ... 」
娘「 いいわけないでしょう! 自分の娘なのよ!」
母「 ... もういいよ。帰ってよ! ... 」
せっかくの面会なのに、母親も娘もイライラし、ケンカになってしまいます。なぜこうなるのでしょう?
例2: 施設で暮らしている認知症の母親と、毎日面会に訪れる娘の会話
娘「お母さん、面会に来ましたよ」
母「あー、お前じゃないか。久しぶりだねえ。長いこと来てくれないので、何かあったんじゃない
かと配していたんだよ」
娘「なに言ってるのよ。毎日ちゃんと面会に来ているじゃない!(ベッド横のカレンダーを指さし
て)カレンダーを見てごらん。昨日も、その前の日も、ちゃんと赤いマルがついているでしょ
う。わすれちゃったの?」
母「だって ... お前のことが心配だったもんで」
娘「他人(ひと)のことより、自分のことを心配したら」
母「 ... 」
娘「お母さん、しっかりしてよ。少しボケが進んだんじゃない?」
母「 ... もういいよ。帰ってよ! ... 」
こうして、楽しいはずの面会が台無しになってしまいます。おそらく娘さんは「もう二度と来るもんか」と穏やかならざる心境になっているでしょう。
小澤勲著『痴呆を生きるということ』(岩波新書)によると、認知症の人には中核症状としてのもの忘れがあり、それが私たちにとって不都合な、理解しにくい行動(周辺症状)を引き起こしていくそうです。ただし、もの忘れのある人のすべてがそうなるわけではなく、そうなるには相手をイライラさせてしまう私たちの接し方(ケアのあり方)が介在していると言うのです。
「例1」の母親には、もの忘れがあります。娘の名前を思い出すことができません。記憶から向け落ちてしまったのです。それなのに「名前を言いなさい」と強く要求されつづけます。母親としては、「ごめんなさい。あなたの名前、忘れちゃった」と正直に告げることができれば、おそらく気持ちもすっきりするでしょうが、それはできません。なぜなら、どこかで見覚えのある、せっかく来てくれた人に対してそんなことを言うのは失礼だと感じているからです。たとえもの忘れがあっても、認知症の人びとは私たちと同じ感情を保っています。それゆえ、追い詰められた苦しさのあまり、「もういいよ。頼むから、そんなことは聞かないでくれ」と訴えるのです。そうした苦しい気持ちを感じ取れずに(それは私たちの鈍感さを証明している)、もし私たちが質問責めを行うとしたら、最後にはイライラしてきて、「もう帰ってよ」と言わせてしまうことになるのです。
では、面会に来た娘さんは、どのように言葉をかけてあげたらいいのでしょう。「わたしの名前を言ってごらん」と質問するかわりに、もし娘さんが「わたし、娘の○子ですよ」と、まず自分から名のってあげたら、おそらく母親は「あー、○子じゃないか。よく来てくれたねえ。うれしいよ」と答えるにちがいありません。こうして楽しい面会がはじまっていきます。
「例2」はどうでしょう。母親が「お前が長いこと来てくれないので、何かあったんじゃないかと心配していたんだよ」と言ったとき、「お母さん、心配かけてごめんね。毎日ちゃんと来るからね」と答えたとしたら、おそらく母親は「ありがとう。お前だけが頼りだから」と続けるでしょう。こうして親子のきずなを確かめあう、すてきな面会がはじまっていくのです。
老親に認知症がはじまると、子供がその進み具合を心配するのは当然です。それで、いろいろ質問してみたくなるのです。しかしもの忘れがあるのですから、忘れてしまったことは答えられません。
質問するかわりに、こちらから、抜け落ちてしまった記憶をおぎなってあげるほうが良い援助につながります。「記憶していなければ答えられないことを質問してはいけない」 ― これはケアの鉄則なのです。あなただって答えられないことを質問されつづけたら、おそらく惨めな気持ちになっていくでしょう。
最後に、以前このコーナーで紹介した「The 36-Hour Day」(ジョンズ・ホプキンス大学出版)という家族介護者向けの本の一部を抜粋します。これは、もの忘れが進み、体力も衰えたため家で暮らせなくなった老婦人「メアリーの事例」です。
「(施設へ移ってからの)メアリーにとって最もうれしかったのは、家族が面会に来てくれることでした。メアリーは、たまには家族の名前を思い出すこともありましたが、たいていは思い出せませんでした。一週間前に訪問してくれたことも覚えていません。それで、ときどき、家族に見捨てられてしまったと愚痴を言っていました。そんなとき、家族は答えに窮しましたが、それでも彼女の弱った体に腕をまわし、手を握ってあげました。あるいは、黙ってそばに座り、ときには歌をうたってあげました。メアリーにとって有難かったことは、家族が、ついさっきメアリーが口にしたことや、先週面会に訪れたことを、むりやり思い出させようとしなかったことです。また、この人は誰、あの人は誰と、矢継ぎ早に彼女に質問を浴びせることもありませんでした。メアリーのなかでは、家族に抱きしめてもらったり、やさしく接してもらうときが最高の時間だったのです。」 (筆者訳)